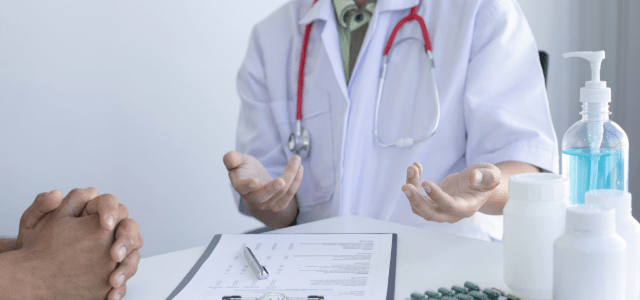
ここでは、短期所得補償保険と長期所得補償保険の違いとして、補償の対応範囲や選ぶポイントなどを詳しく解説します。
所得補償保険は大きく分けて短期補償と長期補償の2つのタイプがあり、保険期間や保険料、免責期間、特約による範囲などに違いがあります。短期補償は短い保険期間であり、病気や怪我の治療で入院する場合や、治療を受けている人で働けなくなった場合に補償されます。また、業務中はもちろん、レジャーや海外旅行中の病気やケガで働けなくなった場合も同じく補償の対象になります。
長期補償は長期の保険期間となっており、病気や怪我の治療で長期間の入院が必要な場合や、自宅療養が必要で就業不能の場合の補償です。短期と同様に医師としての仕事ができないときに補償されます。
てん補期間というのは、免責期間終了日の翌日から起算し、保険金の支払い限度となる期間をいいます。短期補償は、病気や怪我が起きて就業不能になってから、保険金が支払われる期間は1〜2年間と短期です。病気や怪我で治療が必要で仕事ができない状態が、1〜2年程度続くという状況に備えるために加入すると良い保険といえます。また、免責期間(保険金が受け取れない期間)が4日~7日間と短いので、すぐに保険金の受け取りが始まることが最大のメリットです。
一方で、仮にてん補期間1年間の短期所得補償保険に加入していた場合は、就業不能が継続している状態であっても、1年間の補償期間を経過すれば保険金の給付は打ち切りになります。
長期補償においても、病気や怪我によって医師としての仕事ができないときに適用されます。補償期間は最長で満70才までとなっており、保険金を受け取れる期間が長いことが最大のメリットとなっています。ただし、免責期間が60日~372日と短期と比べ長く設定されていますので、短期間の就業時には補償対象となりません。てん補期間は、最長で満70才までのほか、3年間、5年間、10年間と設定できるものがあります。
短期の所得補償保険については、個人事業主が健康保険の代わりに傷病手当金の役割を期待して、多くの個人立の開業医の医師が加入しています。
長期の所得補償保険に関しては、ここ20数年で普及してきた後発の保険になります。既にてん補期間1年間の短期の所得補償に加入されている医師が、免責期間372日の長期の所得補償保険に加入することで、補償の切れ目のないリレープランを設計することができます。
また、開業医の医師の場合は、診療報酬の入金まで約2ヵ月かかることから、入金が途切れるのは3ヵ月後からになります。そこで、長期の所得補償保険の免責期間を60日で設定すれば、万一の就業不能の際も入金の途切れを生まずに保険金を得ることができます。
短期との組み合わせで、就業不能の直後から補償を得ることも設計できますし、短期の所得補償は使わずに長期の所得補償のみに加入し合理的に保険料負担を抑えることも可能です。
一般的に所得水準の高い医師においては、家族も含めた生活水準も高い傾向にあり、就業不能以前のご家族の生活水準を維持するためには、短期(1~2年)の所得補償のみではカバーしきれないため、長期の所得補償保険への加入は、そのリスクヘッジとして必須の選択肢となります。
また、長期の所得補償保険には一部復職という考え方があり、就業不能の期間を経て、就業障害が完治しないままで一部の医師業務に復職しても収入が20%を超えて減少している場合には、その割合に応じて保険金を受け取ることができます。短期の所得補償保険の場合は、一部でも復職をすると保険金の給付がなくなってしまいますが、長期の所得補償保険の場合、就業障害が残っていても保険金の打ち切りを気にすることなく、一部復職にトライすることができます。
短期の所得補償保険は、てん補期間が、1~2年間と短いですが、免責期間も4日や7日と短期間に設定されているため、保険金の給付対象となる機会が多くなります。
一方で、長期の所得補償保険は、てん補期間が、3年間~満70才までと長期、ないし超長期ですが、免責期間が60日や90日、ないし372日と長めに設定されているため、保険金の給付対象となる機会は短期の所得補償よりは少なくなり保険料が抑えられています。
上記のことから、短期と長期の保険料の違いについては、補償期間が長い長期所得補償保険のほうが短期の所得補償保険と比して保険料が高いと思われがちですが、そうとは限らず、契約プランによっては短期の所得補償保険より、長期の所得補償保険のほうが安いケースすらあります。
保険会社や、団体によって契約プランや保険料の違いがありますので、医師向けの保険に詳しい保険のプロに相談するのもおすすめです。
短期と長期で保険金(給付金)支払いを受けるフローに大きな違いはありません。
それぞれの補償では、保険金を受け取れない免責期間が設けられています。短期補償は免責期間が4日~7日と短く、病気や怪我で入院治療が必要となり働けなくなった場合に、すぐに保険金を受け取れることが特徴です。
一方、長期補償は免責期間が60日~372日と長期間となります。所得補償保険は、その保険の性格から保険金の給付は出来るだけに速やかに進めるよう保険会社も対応してくれますが、免責期間(60日や372日)を超えるような長期の就業不能状況が見込まれるときは、保険会社に前倒しで連絡をして、事前にできるところまで保険金請求の手続きを進めておくとよりスムーズに給付手続きが進みます。
また、給付金を受け取れるまでの間、医院の経営や家族の暮らしを守るためのお金は、あらかじめ十分に備えておくことも重要です。
短期補償と長期補償は、保険会社や団体によって選択可能なプランやカスタマイズできる範囲に特徴があります。そのため、選択肢の多さやプランの柔軟性を確認した上で、加入する保険会社を決めることがおすすめです。
短期補償と長期補償どちらでも、給付金の受け取りには適用条件を満たしていることが必須です。病気や怪我により医師として仕事ができない状態であることを証明するために、医師の診断書などの提出が求められます。この際、医師による診断が保険適用の可否判断の基本になります。
短期補償と長期補償どちらでも、保険契約を解約する場合は保険会社に申し出る必要があります。年払いの場合は、未経過期間の保険料を解約返戻金として返金される条件もあるでしょう。契約者の意向による保険契約の解約ではなく、契約が解除となるのは、保険会社の判断によるものです。代表的な例は、加入時の告知事項に虚偽があったケースです。この場合は保険金の支払事由が発生していても、保険金の支払いはできませんが虚偽事項とは無関係の場合には保険金が支払いされることがあります。
医師向け所得補償保険には、短期補償プランと、長期で補償してもらえる長期補償プランがあります。どちらの保険にもメリットとデメリットがありますが、万が一の備えとして加入しておくことがおすすめです。
毎月の保険料や貯蓄額、家族の暮らしを考えて、自身の状況に合った保険を選びましょう。保険会社や団体によっては保険プランを複数選択できることもあり柔軟性やカスタマイズに富んだ保険を選ぶと良いでしょう。
所得補償保険とよく似ている保険に、生命保険会社の取扱う「就業不能保険」があります。補償内容は似ていますが、医師・歯科医師という専門職である場合、直前の業務が補償対象となる所得補償保険のほうが保険適用範囲が広くなります。
さらに長期の所得補償には一部復職の考えもあり、就業不能(就業障害)時における医師としての稼ぎを長期で補償する目的の場合、「長期の所得補償保険」が最も有効な手段と思われます。
参考:就業不能(就業障害)時の各種保険の違い)
| 就業不能保険 | 短期所得補償保険 | 長期就業障害所 得補償保険 |
解説 | |
|---|---|---|---|---|
| 取扱保険会社 | 生命保険会社 | 損害保険会社 | 損害保険会社 | 生命保険会社は、身体の就業不能を補償対象としているのに対し、損害保険は、就業不能(就業障害)による所得の 減少を補償対象としている。 |
| 生命保険料控除 | 対象(介護・医療区分の対象になる) | 対象(介護・医療区分の対象になる) | 対象(介護・医療区分の対象になる) | それぞれ、介護・医療区分の 生命保険料控除の対象になる。 |
| 保険料 | ・年齢・性別・保障内容で決まる ・加入時の保険料が保険期間終了まで続く |
・年齢・補償内容で決まる ・5歳刻みで変動 |
・年齢・性別・補償内容で決まる ・5歳刻みで変動・団体により保険料が異なる |
就業不能保険は、契約時の保険料がそのまま続くが、各所得補償保険は、5歳刻みの年齢区分で保険料が変動する。 |
| 保険期間 | 50才~70才など、 5年刻みで設定できる |
1年更新 | 1年更新 | 就業不能保険は、契約時の手続のみで更新はない。各所得補償は1年更新だが、プラン変更等がない限り基本は 自動更新となる。 |
| 保険金(給付金)額の設定 | ・契約前の年収によって保険会社ごとに上限額の設定あり※保険金額は月額5万円~50万円まで5万円単位で設定が多い | ・契約前12ヵ月間の平均月間所得の50%~70%以下で設定(設定上限は月額200~300万)※個人事業主は70%以下、会社員や公務員は50%以下が多い | ・契約前12ヵ月間の平均月間所得の60%~80%以下で設定(設定上限は月額200~300万)※1口5万円、10万円、20万円等の口数設定が多い | 就業不能保険の保険金月額の上限は、 最大でも月額50万目途だが、 所得補償保険は、月額200~300万までの設定が可能。 |
| 支払条件 | 保険会社によって異なる 例)1. 病気やケガの治療のため入院している状態 2. 病気やケガにより、医師の指示を受け、自宅等で在宅療養をしている状態 |
身体障害を被り、その身体障害の治療のために入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、契約書記載の職業または職務に全く従事できない状態 | 免責期間中は、身体障害発生直前に従事していた業務全く従事できないこと。免責期間経過後は、身体障害発生直前に従事していた業務全く従事できないこと。か、または一部することが できず、かつ所得喪失率20 %超で あること。 | 就業不能保険の場合、障害等級の認定を条件としていたり、入院や在宅(外出できない)であることを条件としているケースがあり、比較的支払条件が厳しい。所得補償の場合、医師としての業務が出来ないことが条件となるため支払い要件は生命保険と比べ認定範囲が広い。 さらに長期の所得補償については、一部復職時の補償も所得の減少率に応じて補償が継続する。 |
| 補償期間(てん補期間)*保険金を受け取れる期間 | 50才~70才など、保険期間設定の年齢まで | 1年間、ないし 2年間 |
3年間、5年間、10年間、満65才まで、満70才まで | 団体によって異なる 短期の所得補償保険は補償期間が短いため、仮に就業不能状態が1~2年以上継続していても補償期間を超えてしまうと保険金の給付は契約時の補償期間をもって打ち切りとなる。 補償期間に良し悪しはないため、自身の目的に沿った保険設計を選択するようにしたい。 |
| 一部復職時の保障(補償) | なし | なし | あり | 上記、支払い条件の通り、長期の所得補償にのみ一部復職時の補償が ついている。 |
| 免責期間 *就業不能状態になってから実際に保険金を受け取れるようになるままでの期間 |
10日、180日間等 1保険会社によって異なる |
4日、ないし 7日 60日、90日、372日等 | 60日、90日、372日等 団体によって異なる | 短期の所得補償保険は、就業不能時の免責期間が短く給付が受けやすいが、補償期間が短い。 |
| 精神疾患の 取り扱い |
一部の商品・プランは精神疾患でも保障対象になる | 基本的に精神疾患は補償対象外 | 特約対応(てん補期間2年間) | 商品や団体によって対応が異なるので 個別に確認が必要。 |
医師としての仕事ができないときに長期的に家族の
生活水準をカバーしてくれるのが「長期所得補償保険」
田伏 秀輝
短期所得補償保険は、短期入院や一時的な治療による就業不能に備えて加入する保険です。医師にはなじみがあり気軽に加入しやすいプランですが、補償期間が短いために、保険金給付満了後の保険について考える必要があるでしょう。
長期所得補償保険は、長期的な入院や自宅療養による就業不能に備えて加入する保険です。最長で満70才までの補償期間であり、長期にわたり補償してもらえることはメリットとなります。
所得の高い医師の場合、ご家族の生活水準も高くなる傾向があり、高い所得を前提とした生活をしていることが多いです。例えば、子供が目指す大学の選択肢も所得水準により大きく変化してしまいます。高い所得水準に保険金額を設定することで、もしもの場合もご家族の生活水準を変えることなく、補償を受け取り続けることが可能です。
短期間の収入減少に備えるためには短期補償保険を検討し、長期の就業不能に備えておきたい場合は長期補償保険を検討してみましょう。