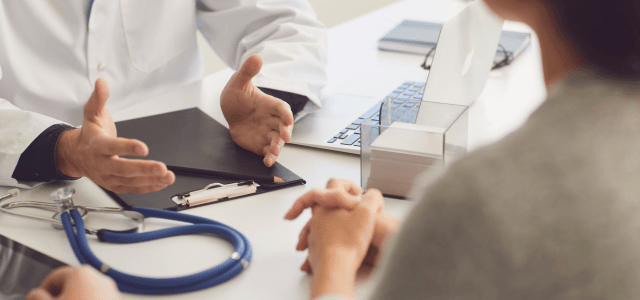
産婦人科における訴訟事例では、分娩に関連した事例が多くみられます。日本の周産期死亡率は世界でも低いですが、それでも胎児・新生児が亡くなる、または神経障害が残ってしまうなどの事例は発生しています(※)。
※参照元:医療安全推進者ネットワーク(https://www.medsafe.net/specialist/9nakabayashi.html)
産婦人科医師における大きな訴訟事件と言えば、2004年に福島県立大野病院で妊婦が死亡し、担当医が逮捕・起訴された大野病院事件(※)が挙げられます。刑事訴訟まで発展するケースは稀であり、最終的には無罪となりましたが、全国の産婦人科医師や医療関係者への影響は大きいものでした。
日本の出産における周産期死亡率、妊産婦死亡率は世界でも低いのですが、産婦人科医師が訴訟を起こされるリスクは決して少なくありません。その理由としては、お産は病気ではないことから基本的に保険が適用されず、出産リスクを軽く捉えられているからです。また、胎児・新生児・妊産婦と若いので、死亡や後遺症の残る障害で失われるものが大きいのも関係しています。
※参照元:日経メディカル(https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/clinic/jinho/202304/579144.html)
出産における安全性は日々向上していますが、訴訟リスクは相変わらずであり、産婦人科医師を中心に現場での懸念事項になっています。
こうした現状から産婦人科医師を守るため、無過失補償制度が創設されています。これは、過失の有無に限らず、妊娠・出産で問題が見られたら一定額の補償金を支払うというシステムです。2009年1月には、産科医療補償制度としてスタートし、現在は脳性麻痺を対象にしています。そうした対策で、産婦人科における訴訟件数の減少に働きかけています。
産婦人科では、出産リスクに備えて産科診療ガイドラインを作成しています。産婦人科での医療ミスは、この産科診療ガイドラインの心配を無視した行動から起こっているともいえます。そのため、産婦人科医師が訴訟に巻き込まれた場合では、病院としても産科診療ガイドラインに沿った適切な診療が行われていたのかを確認し、その結果で医師への対応が決まるともいえます。
勤務先の病院の訴訟における対応は一概には言えませんが、先に挙げた大野病院事件では、該当する医師は起訴中は休職中扱いとなり、無罪判決後は同病院に復職しています。また、よほどのことがなければ、訴訟は医師個人よりも病院を相手取って行われるので、病院側も明らかな医師による過失がなければ突き放すような対応はしないと考えられます。顧問弁護士を通した対応が行われるでしょう。
医師賠償責任保険とは、不測の医療事故が発生した場合の補償をカバーする保険です。研修医についても例外ではなくなってきています。日本産科婦人科学会では、勤務医師賠償責任保険や産業医等活動保険など複数の保険を取り扱っています。保険によっては団体割引が適用されます。
医師賠償責任保険では、医療行為に起因する事故における賠償責任が補償されます。補償上限額は1事故あたり1~2億円に設定されていることが多く、超過した分が自己負担となります。後遺障害慰謝料や逸失利益だけでなく、ケースによっては長期の介護料から損害賠償金が1億円を超えることもありますので、十分な補償上限額の検討が必要です。
将来性からも賠償金額は大きくなりがち
田伏 秀輝
万全の体制を整えていても、予期せぬことが起こるのが医療現場です。特に産婦人科は胎児・新生児・妊婦さんと、多くの症例がある病気とは異なる現場。
また、妊娠・出産は病気ではない事からも、生じた結果についての受け止め方も様々です。若い命への訴訟だけに、賠償金額は大きくなりがちですから、医師賠償責任保険に加入しておくと安心です。産科脳性麻痺などでは、後遺障害慰謝料や逸失利益から1億円を超える事例も多く見られています。